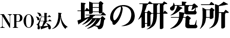このメールニュースはNPO法人「場の研究所」のメンバー、「場の研究所」のイベントに参加された方を対象に送付させていただいています。
□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□
■場の研究所からのお知らせ
□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□
皆様
10月になりました。ようやく涼しい日が訪れて、一息ついていらっしゃるのではないでしょうか?また、トンボなど秋の気配も感じられて、嬉しい気持ちになっているこの頃です
さて、8月は夏休みをいただいたので、間が空きましたが、9月は第4金曜日の26日勉強会が開催されました。まだ先日終わったばかりですが、今月のメールニュースをお送りいたします。
まずは、ご参加下さった方々ありがとうございました。
先月は『共存在の進化』という楽譜で議論をしました。
大相撲の土俵が土と水と塩でできていることや、力士が神聖な舞台でその役割を果たすことなど多くの気づきが得られたと思います。
9月のテキスト(楽譜)の内容については、下記にまとめてありますので、参加されなかった方も是非参考にして下さい。
今月の勉強会ですが、第3金曜日が17日となるため、第4金曜日の24日に開催したいと思います。(第3金曜日が20日以前になる場合は、勉強会は第4金曜日におこないます。)
もし、勉強会について、ご感想・ご意見がある方は、下記メールアドレスへお送りください。今後の進め方に反映していきたいと思います。
contact.banokenkyujo@gmail.com
メールの件名には、「ネットを介した勉強会について」と記していただけると幸いです。
(場の研究所 前川泰久)
◎2025年9月の「ネットを介した勉強会」の内容の紹介
第60回「ネットを介した勉強会」の楽譜 (清水 博先生作成)
★楽譜テーマ:『共存在の進化』
◇個物的生命体と場所的生命体について
・生きていること(状態)は宇宙に地球として存在しているということ、死んでいること(状態)も同様に宇宙に地球として存在しているということから、地球における共存在が個物的生命体(生きもの)の中心的なテーマであると考えられる。
・そこで生きもの(個物的生命体)を「役者」とし、場所としての地球(場所的生命体)を「舞台」として、「〈生命〉のドラマ」を演じていくことになる。ただし「役者」も「舞台」も共に宇宙における天体としての地球である。
◇共存在が生まれるための土の必要性について
・共存在の場所である地球は、このように、矛盾的自己同一(一即多、多即一)の形をしているが、しかし矛盾的自己同一だけでは、「〈生命〉のドラマ」のストーリー(物語)は生まれない。
・物語が生まれるためには、共存在に向かってはたらく活きが必要である。共存在が生まれるためには、たとえば土が必要である。土があってこそ、植物は芽を出すことができるし、また植物があってこそ、動物が生きることができる。
・”「土」のざくっとした定義は「岩の分解したものと死んだ動植物が混ざったもの」。だから、生命の存在しない月や火星には、土はない…”(鈴木大樹さんによる7月の勉強会の1通目より)。
・つまり、地球における共存在によって生まれたものである。共存在に向かって、「舞台」としての地球の上の状態を進める活きがドラマの物語をつくると考えられるのである。
◇共存在における広さの限定における例としての土俵
・共存在を可能にする土の広さに限定があり、あまり狭い場所では、複数の個物的生命体は同時に存在していくことができないと思われる。
・このことを表現しているのが大相撲の土俵である。土俵は混じりけのない土でできている。そして力士は裸になって水と塩で純粋な〈生命〉の共存在の形をつくり、そこで共存在しようとするが、土の広さに厳密な限界があり、その上に複数の力士が共存在することはできない。
・その土俵の上に一人だけ存在するようになるように、一方が他方を土俵から押し出すことが相撲の基本的な勝敗(物語)である。
◇大相撲を例にした共存在の見方
・大相撲は結局、地球の土における共存在の必要性を、土俵という場所を狭くして、土の広さに限界をつけることによってネガティブな側から表現しているのである。
・ポジティブな側から見直せば、結局、「役者」の共存在の状態を「舞台」としての土の上で進めることが、「〈生命〉のドラマ」の物語をつくることになるのである。
◇生物の進化とは「〈生命〉のドラマ」(共存在のドラマ)の進化
・生物進化とは、地球を場所的生命体とする「〈生命〉のドラマ」(共存在のドラマ)であり、単に個物的生命体(「役者」)としての生きもの「演技」の進化――新しい生きものの出現――ではない。
・それは「〈生命〉のドラマ」(「舞台」と「役者」が表現する物語)の進化なのである。つまり、共存在の進化なのである。「舞台」と「役者」は互いに関係し合って進化していく(ドラマを創造的につくり出していく)のである。
・生と死を越えることができて、はじめて「地球としての存在」という観点に立つことができる。
・「地球としての自己」の〈生命〉の存在では、地球における個物的生命体の共存在が生み出す与贈循環の圧力によってストーリー(物語)が生まれて、進化しながら変化をしていく活きが存在しているので、ドラマの形ができるのである。
・このように生物進化の本質は、地球における共存在が生み出すストーリー(物語)のある「〈生命〉のドラマ」なのである。
◇共存在しながら「〈生命〉のドラマ」の物語を背負うことの重要性
・大相撲は見方を少し変えると、「人々は場所(土俵)としての地球に共存在しているけれど、「〈生命〉のドラマ」の物語を背負って、「役者」として自己の〈生命〉を生きることができるのは一回の人生だけ」ということを表現している可能性もある。
・大相撲の熱気は、力士と観客がつくり出す「〈生命〉のドラマ」の熱気なのである。
(資料抜粋まとめ:前川泰久)
◎10月の「ネットを介した勉強会」開催について
楽譜のテーマ:『共存在と〈いのち〉のドラマ』
10月24日(第4金曜日)の17時よりの開催予定です。
ご期待ください。
これまでご参加下さっている方には、ご参加希望についてのお知らせを別途お送りします。
なお、新規に参加ご希望の方も、問い合わせメールアドレスへご連絡ください。
開催に際しては、場の研究所スタッフと有志の方にご協力いただき、メーリングリスト(相互に一斉送信のできる電子メールの仕組み)を使った方法で、参加の方には事前にご連絡いたします。
この勉強会に参加することは相互誘導合致がどのように生まれて、どのように進行し、つながりがどのように生まれていくかを、自分自身で実践的に経験していくことになります。
参加される方には別途、進め方含め、こばやし研究員からご案内させていただき、勉強会の資料も送ります。(参加費は無料です。)
もし、勉強会について、ご感想・ご意見がある方は、下記メールアドレスへお送りください。今後の進め方に反映していきたいと思います。
contact.banokenkyujo@gmail.com
メールの件名には、「ネットを介した勉強会について」と記していただけると幸いです。
なお、メールニュースが毎月届いていらっしゃらない方は、是非、ご連絡ください。
2025年10月5日
場の研究所 前川泰久