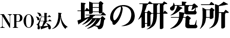メールニュース
※ このメールニュースは、NPO法人場の研究所のメンバー、場の研究所の関係者と名刺交換された方を対象に送付させていただいています。
※ 「メールニュース」は、場の研究所メールニュースのバックナンバーを掲載しています。
2026年分
場の研究所メールニュース 2026年01月号
このメールニュースはNPO法人「場の研究所」のメンバー、「場の研究所」のイベントに参加された方を対象に送付させていただいています。
□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□
■場の研究所からのお知らせ
□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□━□
皆様
いよいよ師走になり今年も最後の月となりました。年末で皆様お忙しいかと思います。
昨今、急にインフルエンザの流行となっていますので是非体調にお気を付けください。
さて、11月の勉強会に、ご参加下さった方々ありがとうございました。
先月は『世界における共存在(「世間よし」)』という楽譜で議論をしました。
アメリカのトランプ大統領の政治運営と近江商人の「三方よし」との比較などから共存在の重要性について学びました。
11月のテキスト(楽譜)の内容については、下記にまとめてありますので、参加されなかった方も是非参考にして下さい。
12月の勉強会ですが、第3金曜日の19日に開催したいと思います。
お忙しいとは思いますが、是非ご参加いただければと思います。
もし、勉強会について、ご感想・ご意見がある方は、下記メールアドレスへお送りください。今後の進め方に反映していきたいと思います。
contact.banokenkyujo@gmail.com
メールの件名には、「ネットを介した勉強会について」と記していただけると幸いです。
(場の研究所 前川泰久)
◎2025年11月の「ネットを介した勉強会」の内容の紹介
第62回「ネットを介した勉強会」の楽譜 (清水 博先生作成)
★楽譜テーマ:『世界における共存在(「世間よし」)』
◇人々が共存在していくには
・一つの世界で人々が共存在していくには、二つの方法がある。
第一は、世界を場所としておこなう与贈循環。
第二は、近江商人の「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」。
◇第一の方法について
・第一の方法は、持てるものが持てないものに与贈するわけであるから最も直接的で無駄がない。しかし、与贈するものと与贈されるものの存在が固定されてしまう可能性があり、そうなると続かなくなる。
・この固定された与贈循環という現象が人々の存在の自由に対する制限として、現在、地球に広く広がっている。もう、これまでのように、人々は存在の自由を主張することができない。
・「どうして地球に共存在していくか?」ということが、緊急かつ最重要な問題として、人間の前に大きく浮かび上がってきたのである。
◇存在の多様性への反発
・存在の自由の結果生まれるのが存在の多様性であるが、難民を受け入れる多様性の国として有名なオランダでも、反難民を主張する右翼政党の動きが強まっていると言われている。
・難民を自分たちと同じ国民として受け入れることは、大きく考えればその難民を生み出している国民へ与贈することと同じである。オランダの状態がこれであるから、ヨーロッパの他の国では反難民の動きはもっと強いと思われる。
・ハーバード大学における人々の存在と学問の自由を新しく制限しようとしているアメリカにも、その制限が一流大学一般に実質的に広く広がっており、大学の人々は口をつぐんで生きていくより方法がないようである。
◇存在の多様性を支える国連の衰退
・世界における人々の存在の自由とその多様性を護ることを目的にして作られたのが国際連合であるが、その頭脳の活きとも言える安全保障理事会にアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の常任理事国をつくり、しかもその国々にのみ拒否権を与えたことが結果的に世界における人々の存在の多様性と共存在を否定することになってしまった。
◇第二の方法について:共存在の方法としての「三方よし」とディールの比較
・このような行き詰まりのなかで新しい共存在の方法として、その可能性が浮かび上がってきたのが、「三方よし」の方法である。これは世間が認める相場によって商品の値段が決まることを意味している。
・その具体的な形の例となっているのが、アメリカの大統領トランプの「ディール」である。ディールと表現する以上、「売り手よし」と「買い手よし」を前提にしている。
・そして、もしも、トランプ本人が自己の仕事がノーベル平和賞に値すると考えているように、そのディールが世界における人々の共存在のために新しい可能性を開けば、それは「世間よし」になっている筈である。
・もしも、これまでの国連では解決できない共存在上のトラブルを、トランプが彼のディールという方法によって解決していくのなら、それは「三方よし」の形になっているし、彼自身が考えているように、ノーベル平和賞に値するのではないかと思う。
◇ディールは本当に「三方よし」に繋がるか?
・トランプのディールはこのように「三方よし」につながっている可能性があるので、これまでの「左翼、右翼」の右翼とはまったく質が異なっている。
・ただ問題は売り手と買い手の間の「相場」を決める「世間」が地球ではなくて、トランプの「共和党のアメリカ」であるということであろうか。近江商人の「三方よし」のように一般化できるかどうか不明である。
・中国が考えているように、そのうちに矛盾が現れて、破綻してくる可能性がある。
・トランプがよく使う「左翼」という言葉はディールの観点(売り手と買い手という観点)から言えば間違っている。正確には、「世間(地球)の相場から外れている」と言うべきである。
・そのために、ディールの観点から言えば、「三方よし」の形で地球の上の世界に一般化することができないのである。
・日本のマスコミでよく使われる「右翼」という言葉も、同様な意味において間違っている。
◇与贈循環の軽視か否定の傾向
・第一の世界における国連中心の与贈循環の方法を軽視するか否定して、トランプに併せようとする第二の動きは、世界でいろいろ生まれてくると思われる。
・日本の高市内閣もそのような共存在の流れの中で生まれた活きだと思う。
・これは、その原因を深く考えると、地球という「世間」(世界)が狭くなってきたことからおきる「相場」の変化であるから、逃れることはできない。
◇「世間よし」から「地球よし」への転換
・学問や医療におけるものの見方も、そのような地球文明の大きな変化によって変わっていく可能性があるが、それに合わせるためには、ディールというものの見方を、「世間よし」を新しく生み出すように広げていく必要がある。
・そのためには、「世間よし」を「地球よし」の形にして、その「相場」を生成していくことを考える必要がある。事実、そのように文明は変化をしていくと考えられる。
◇「世間逆拡大の法則」について
・「世間よし」の「世間」としての地球が実質的に狭くなるということは、意識して生きていかなければならない「地球」が逆に広くなり、その「世間」に対して「売り手よし」という活きと、「買い手よし」という意識とが求められてくるということである。
・地球のような居場所が狭くなるほど、逆に「世間」は広くなっていくことを「世間逆拡大の法則」と名付けておく。
◇共存在に不可欠な与贈循環
・さらに個人レベルの私的な生活は、特別な例外以外は、住居がある地域の空間のなかでおこなわれるので、与贈循環によって直接的につながる形で進行していく。
・その結果、地球という広い「世間」での相場が進めば進むほど、与贈循環という直接的な方法が個人のレベルでは強く求められてくる。
(資料抜粋まとめ:前川泰久)
◎12月の「ネットを介した勉強会」開催について
楽譜のテーマ:『場と三方よし』
12月19日(第3金曜日)の17時よりの開催予定です。
ご期待ください。
これまでご参加下さっている方には、ご参加希望についてのお知らせを別途お送りします。
なお、新規に参加ご希望の方も、問い合わせメールアドレスへご連絡ください。
開催に際しては、場の研究所スタッフと有志の方にご協力いただき、メーリングリスト(相互に一斉送信のできる電子メールの仕組み)を使った方法で、参加の方には事前にご連絡いたします。
この勉強会に参加することは相互誘導合致がどのように生まれて、どのように進行し、つながりがどのように生まれていくかを、自分自身で実践的に経験していくことになります。
参加される方には別途、進め方含め、こばやし研究員からご案内させていただき、勉強会の資料も送ります。(参加費は無料です。)
もし、勉強会について、ご感想・ご意見がある方は、下記メールアドレスへお送りください。今後の進め方に反映していきたいと思います。
contact.banokenkyujo@gmail.com
メールの件名には、「ネットを介した勉強会について」と記していただけると幸いです。
なお、メールニュースが毎月届いていらっしゃらない方は、是非、ご連絡ください。
2025年12月1日
場の研究所 前川泰久